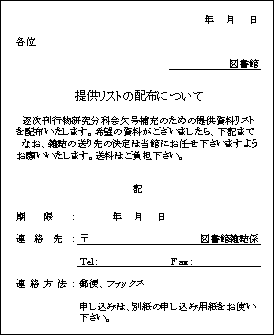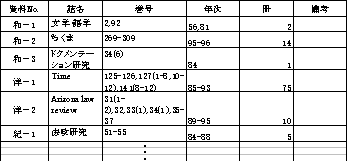逐刊分科会マニュアル 1997年度版(改訂版)
私立大学図書館協会東地区部会研究部
逐次刊行物研究分科会
1997年7月発行
1992年度版マニュアル作成
案作成:逐刊分科会マニュアル作成委員会
案修正:逐刊分科会マニュアル作成委員会(1992.4.11)
(世話人) 中村保彦 文教大学湘南図書館
(事務局長) 中嶋基仁 日本体育大学図書館
(企画委員) 金子登志緒 大東文化大学60周年記念図書館
1997年度版(改訂版)マニュアル発行に際して
1992年版のマニュアル発行より5年程経て、このたび1997年版(改訂版)を発行することとなった。本版では基本的内容や編集スタイルは1992年版を踏襲しつつ、主として誤植の修正・呼称の変更(「世話人」→「代表」、「相互協力」→「資料交換」など)・データの差し替え(「参考文献リスト」など)・語句の統一などを行った。その他「資料交換」の項目のように記載量を増やした箇所もある。
これによって、より分科会活動がスムーズに遂行されれば幸甚である。
逐刊分科会運営委員会(1997.7.1)
マニュアル改正:マニュアルの内容は、少なくとも2年1期を経過するごとに運営委員会で審議し、改正・追加・廃棄をする。
はじめに マニュアルの目的
[活動を体系化する]
逐次刊行物(研究)分科会は、第1回の研究会を国際基督教大学(1956年2月23日、世話人:鬼頭當子氏)で開いて以来、歴史の長い研究会である。その間、多くの会員が逐次刊行物に関する様々なテーマを取り上げてきた(『逐次刊行物研究分科会報告』42号所載の年表を参照)。
けれども、活動の歴史・多様性に反して、活動の内容や方向を明示する正式な文書は存在していなかった。そこで、円滑な研究活動を支援するため、従来のメモや伝言・慣例ですませていた内容をマニュアルとして集大成し、研究会の独自性を活動面で体系化することを考えた。
[工夫を修正記する]
上述のように、『逐刊分科会マニュアル』作成の目的は、当逐次刊行物研究分科会の円滑な運営と研究活動の充実のためにある。同時に、会員の研究活動に関する共通理解が得られるようにとの思いも含まれている。また、私立大学図書館協会の研究分科会活動として守ってほしい最低限のルールも含まれている。それとは別に、マニュアルの内容は、自由な研究活動を支援するのものでなくては作成の主旨に反する。「動中の工夫は静中の工夫にまさる」というように、現実に合わない点、不都合な点があれば、それを直していかなければ、マニュアルは役に立たない。すなわち、実務の中で工夫された技術が把握され、文章として表現され、集積されてこそ意味がある。このマニュアルも、各期の会員によって改版が続けられ、内容が批判的に継承されることを理想として作成した。
[マニュアルを利用する]
目次には、現時点で整理し得る研究活動の内容を項目として設定した。内容の改正による差し替えを用意にするため、1項目1ページとした。会員は全体を通読してもよいし、必要な項目だけ読んでもかまわない。また、研究会が会員全員で運営されるように、事務局の作業を示した項目でも一般の項目と区別しなかった。
1992年3月31日
世話人 中村保彦
(文教大学湘南図書館)
1. 研究活動の基本
1.1 研究の基本テーマ
基本となるテーマ
逐次刊行物研究分科会は、以下の諸点を研究活動の基本テーマとする。
1) 資料研究
大学図書館における学術資料・専門資料としての逐次刊行物の研究。
2) 実現可能性研究
図書館業務における逐次刊行物業務の可能性と実践理論の追求。
3) 個別的方法論の追求
会員各自の問題意識を出発点とし、図書館情報学などの学問的成果を批判的に吸収
しつつ、個別の方法論を追求する。
研究活動の計画
上記の基本テーマを前提として、各期の具体的な研究計画は、会員募集要領にその都度提示する。研究計画の内容は、前期の運営委員会で立案し決定する。ただし、①代表・運営委員会が交代した場合、②会員の要望が多数の場合は、研究計画の変更を可能とする。また、現在、月例会で継続して行っている研究活動の内容は次のとおりである。
1) 個人研究発表
会員1人、各期に最低1回の発表を基本とする。(テーマ自由)
2) 共同研究
大学図書館会の状況に応じて、会員に共通した問題がある場合は、それらをテーマと
して共同研究のグループを結成する。(全員参加)
3) 相互協力
1976年(S.51)に第1回「欠号補充を主目的とする相互協力」がスタートして以来、毎年
継続して行っている。重複資料交換のための提供リストは、原則として大学の繁忙期を
除いた月例会で随時、配布する。
* 情報交換
その他、副次的な活動として種々の情報交換、アンケート調査を行う。ただし、それらの
結果は内部資料として公表しない。(原則)
例)外国雑誌リニュアルの為替レート、雑誌製本業者の比較
1.2 研究対象の範囲
逐刊を定義する
逐次刊行物の一般的な定義を知り、その背景にある実務的な問題をつかむ。
逐次刊行物の定義
「一つの標題を持ち、通常、巻次または年月次を持ち、終期を予定せず継続して刊行する
もの」
* 逐刊である=①同一名称を持っている → 改題の基準は何か
① 号をおって刊行される → 巻次年月次の形式把握のむずかしさ
② 終刊を予定しない → 休刊・廃刊をどう決定するか
種類を把握する
① 定期刊行物、雑誌Journals, Periodicals
② 新聞Newspapers
③ 年刊出版物、年報、年鑑Annuals, Yearbooks, Reports
④ 紀要、研究報告、論文集Memoirs, Bulletins
⑤ 議事録、会報Proceedings
⑥ 会報、業務報告Transactions
⑦ モノグラフ・シリーズMonographic series
⑧ 出版者叢書Publishers series
⑨ 年刊展望類Annual review type literature
定義と取扱いとのちがい、逐次刊行物と図書の中間領域にある資料にも注意する。
cf.『資料整理法持論』(長谷川宏、成井恵子共著、東京書籍)p.19
対象の範囲を知る
1) 業務の対象を知る
逐刊の定義と具体的な種類を把握して、自館が業務の対象とする範囲を知る。
①発注・受入・整理 ②登録・製本の有無 ③貸出の可否など
2) 研究対象の限定
画異論的な内容や新人研修的内容は、研究活動の主旨に外れるため、原則として扱
わない。会員は、適宜、参考文献リストなどから選択して学ぶこと。
cf.マニュアル付録「参考文献リスト」
1.3 研究活動方針
研究活動の目的
逐次刊行物研究分科会は「私立大学図書館協会東地区部会研究部研究分科会申し合わせ」(以下「申し合わせ」と略す)に則った活動を行い、大学図書館における学術資料である逐次刊行物に関する共同研究およびその知識の普及、を研究活動の目的とする。
研究期間、発表
1) 原則
研究活動の期間は1期(2年間)を単位とする(「申し合わせ」第5条)。各期毎に研究計
画を立案し、常任幹事会に提出する。
2) 発表
研究成果は、原則として「逐次刊行物研究分科会報告」に発表する。また、各期の期
間中に1回以上、私立大学図書館協会東地区部会研究部で研究発表を行う。
3) 継続
研究期間の更新を前提として、共同研究中のテーマについて、その研究期間を2期以
上にわたって継続することを可能とする。ただし、継続する場合は、中間報告を1期毎
に行う。
会員募集要領
代表・各運営委員は運営委員会を構成し、運営委員会は次期「会員募集要領」を作成する。また、会員募集要領の作成に際して、現会員の意見・希望を反映するよう努める。なお、これは「申し合わせ」第3条の定める参加者選定の基準項目に従って作成する。
cf.「会員募集要領」
① 当該期間の研究テーマ
② 研究回数
③ 当該テーマの研究に必要とされる条件
④ 会費徴収額
募集要領(1996)

2. 研究活動の内容
2.1 運営
2.1.1. 運営委員会
運営委員会の構成
1) 委員
運営委員会は代表をはじめとする各運営委員によって構成される。各委員は、研究活動
が円滑に進むよう代表を中心に分科会を運営する。分科会全体で検討すべき内容につ
いては、月例会で協議する。
2) 構成
運営委員の数は原則として各1名。必要に応じて2名まで可能とする。
代表:会の全般的な運営、対外的な交渉、私大図協合同会議の出席
運営委員長:代表の補佐および代行、会全体の運営に関する協力
会計:年会費徴収、予算・通帳・帳票などの管理、年度の会計報告
企画:月例会、夏期研究合宿の企画・運営
広報:月例会などの受付・出欠・配布資料の管理、議事録の作成
編集:(報告書担当)報告書の編集、原稿・広告の依頼、報告書予算管理、報告書管
理、発送リスト管理
(逐刊ニュース担当)逐刊ニュースの編集・作成、管理
相互協力:資料交換作業の管理・運営、実績調査と報告の作成
運営委員の選出
1) 選出
代表は月例会における会員の承認または協議により選出する。他の運営委員は代表
が依頼し、会員に意義がなければ選出を可能とする。
2) 任期
運営委員の任期は、原則として1期2年間とする。再任は妨げない。ただし、研究活動
の活性化を維持するために、任期は連続しても2期位で交代するのが望ましい。
3) 交替
所属大学および会員本人の事情により、運営委員が各期の途中で交代する場合は、
運営委員会の協議を経て交替する。その場合は後任者を推薦すること。
研究計画の立案
運営委員は、運営委員会において研究計画の立案を行う。計画の概要が決定した時点で、
次期会員募集要領の「研究計画(予定)」の原稿とする。
2.1.2. 研究活動の管理
研究の水準を保つ
研究活動を円滑に進めるためには、ある種の管理が必要である。管理は監視・統制とはちがい、研究がうまく行われるためのルール設定・調査・修正を意味する。
1) 研究活動の管理
「研究活動の管理とは、研究を一定の水準に保つことである」
2) 事務的作業の本質
運営委員は、研究を達成(サポート)するための事務的作業を行う。
① 目的・合理的遂行
② 脱肉体的行為(誰が行っても同じ結果が出せるように)→簡素化、正確さ
③ 情報(ノウハウ)伝達行為→迅速性、明確さ
研究活動をチェックする
研究活動は会員の自主的な参加が前提である。それゆえ、会員の自己管理が重要になる。「お客様意識」は管理されることと同じであり、研究に結びつかない。
1) 基本項目
① 展望:将来の展望・計画、業務と活動、機能・質
② 考え:目的、業務、活動計画、図書館情報学、改善案、図書館界、位置づけ
③ 活動:研究相互の関係、研究活動の流れ、事務作業
④ 運営:コミュニケーション=創造性、少数意見、協力関係、議論、発表、準備、司会
⑤ 資料:研究活動で発生する資料=レジュメ、マニュアル、ニュース・報告書など
⑥ 組織:研究会の組織運営、存在理由、意志決定
⑦ 調査:現状把握、研究時間、問題発見
cf.マニュアル「研究活動 チェックリスト」
2) 自己管理
研究活動活性化の前提=環境+能力+意欲
① 環境:研究会の組織に問題があるか、あれば改善は可能か
② 能力:自分の能力に制限があるか、あればどう学べばよいか
意欲:研究する気があるか、どう持続していくか
研究活動 チェックリスト
研究活動を管理するために大枠となる基本項目とそれに含まれるチェック項目を設定した。
管理の目的は研究会の活性化であり、項目はそのための目安にすぎない。
�
| 基本項目 |
チェック項目 |
| 1) 展 望 |
□ |
将来のビジョン(2年前)を考えているか |
|
□ |
業務に役立つ活動とは何か |
|
□ |
研究活動の機能・質をどう高めるか |
| 2) 考 え |
□ |
研究活動の目的を考えているか |
|
□ |
逐次刊行物業務の混沌をどう整理するか |
|
□ |
会員の研究活動は計画的におこなわれているか |
|
□ |
図書館情報学の成果を学んでいるか |
|
□ |
研究湯活動の改善策を出しているか |
|
□ |
図書館界の状況を広く把握しているか |
|
□ |
私大図協における研究会の位置づけはどうか |
| 3) 活 動 |
□ |
研究相互の関連を把握しているか |
|
□ |
会員の研究活動はスムーズか |
|
□ |
事務的作業のサイクルはうまくいっているか |
| 4) 運 営 |
□ |
月例会の集団的創造性はどうか |
|
□ |
少数意見を尊重しているか |
|
□ |
結論を導くための会員間の相互協力はよいか |
|
□ |
会員の真面目な議論が形成されているか |
|
□ |
会員に対する研究発表依頼の状況はよいか |
|
□ |
事前準備はうまくいっているか |
|
□ |
司会者のコントロールはよいか |
| 5) 資 料 |
□ |
事前配布資料(レジュメ他)の準備はよいか |
|
□ |
マニュアル類を整備しているか |
|
□ |
『逐刊ニュース』、『分科会報告』の発行は順調か |
| 6) 組 織 |
□ |
硬直化・マンネリ化に注意しているか |
|
□ |
研究会の存在理由に合っているか |
|
□ |
意志決定は迅速で妥当か |
| 7) 調 査 |
□ |
会員の現状を把握しているか |
|
□ |
研究内容と時間のバランスはよいか |
|
□ |
逐刊業務にどのような問題点があるか |
2.2. 参加
2.2.1. 会員の研究活動
現在位置を知る
1) 業務環境の把握
「社会→大学→図書館→逐次刊行物係」と考え、自分が受け持つ業務に関するイメー
ジを明確にする。また、業務を取り巻く環境(能力、制限、可能性)を把握する。
2) 担当業務の現状
担当する業務内容の過去・現在・未来を考える。「担当業務調査表」などによって現状
を具体的に把握し、改善方法を発見する。また、現在に至るまでの業務内容の変化・追
加を「評価付き年表」にまとめるのも有効な方法である。
3) 研究目的を自覚する
上記 1) 2) を考慮した上で、何のために(目的)・何をしようとして(計画)参加するのか
を明確にする。漠然と参加しても時間の無駄。
研究方法をつかむ
1) 研究方法の基本
自分なりに、調べる(読む)、発言する(議論)、書く(報告)スタイルをつかむ。
* その類の参考になる一般書は多く出版されているので、適宜、読んでおくこと。
2) 研究方法の要件
① 課題:研究を必要とする課題(問題点)を発見しているか
② 個性:その課題を研究する場合、個性を生かした方法で研究することが可能か
③ 支持:その方法は分科会内で理解され、支持され得るものか
主体的に発言する
1) 議論のトレーニング
会員にはテーマに対して主体的に発言する権利と義務がある。したがって、生産的な
議論を形成するために、①多数意見への同調、②強行意見への追従、③自説に固執
した拒否的態度、をなるべく避ける。
2) 発言内容の要約化
会員全員が月例会の限られた時間内で発言するために、1回の発言を要領よくまとめ
て行うこと。
2.2.2 月例会
月例会の開催
1) 回数
年10回、学年暦(4月-3月)単位で開催する(8月・2月は休会)。
2) 日時
開催曜日は、前年度の「次期会員募集要項」作成時に案を常任幹事会へ提出。他の
研究分科会の開催曜日と調整して決定する。時間は午後1時から5時。
3) 会場
月例会の会場は、原則として会員が所属する大学のもちまわりとする。
4) 内容
個人研究発表、共同研究、図書館見学を中心とし、講演などはその都度設定する。
5) 進行
司会は会員のもちまわりとし、代表が依頼する。
6) 夏期研究合宿
9月の月例会を夏期研究合宿として開催する。その目的は、通常の月例会で実現が困
難な研究・学習を行う点にある(費用別途)。
7) 二次会
研究活動を円滑に進めていくために、二次会を開催する場合がある。ただし、参加は
任意。慣例として、始会・忘年会・納会は開催する。準備は会場校の会員が行う。
出席の準備をする
1) 準備
『逐刊ニュース』の連絡などを熟読する。月例会の案内は、『逐刊ニュース』と私大図協
の「開催予定表」で連絡する。個別には連絡しない。また、月例会で取り上げるテーマ・
問題を把握し、研究に参加できるよう準備する。
2) 連絡
① 欠 席:業務上、特別な場合と病気などの場合を除いて月例会には欠席しないように
する。理由があって欠席する場合は代表に必ず連絡する。連絡なく欠席が続
く会員は退会扱いとし、所属大学図書館の責任者に通知する。
② その他:遅刻、レジュメの送付、機器の使用など個別の用がある場合は、あらかじめ
代表か会場校の会員に連絡・依頼する。
2.3. 内容
2.3.1. 個人研究発表
テーマを決める
1) 発表依頼
代表が発表者に前もって(2ヶ月以上前)発表依頼する。
2) テーマ設定
会員は発表以来を受けた後、早めにテーマを設定し、代表に連絡する。原則として、逐
次刊行物(業務)に関するものをテーマとする。
cf.『逐次刊行物分科会報告』バックナンバー掲載の既発表テーマも参考にする。
研究を進める
「研究」活動は、調査・報告・案内などを含む広義の研究として考える。
1) 調査をする
設定した問題について種々の方法によって調査し、データを集める。同時に、文献を調
査し、参考文献リストを作成する。
2) 問題を提示する
調べたデータや参考文献を中心にして問題を提示する。その場合、稚拙でもオリジナ
ルな意見を持つことが重要。自己評価のないデータや文献の羅列は研究にならない。
3) 発表準備をする
① 資料:レジュメ、参考資料、参考文献リスト(会員数コピー)
② 形式:A4あるいはA3二つ折り数枚程度、日付(西暦)・発表者名・大学名を明記
③ 時間:(原則)発表20分、質疑10分
cf.『理科系の作文技術』(木下是雄著、中公新書)
『読み書きの技法』(小河原誠著、ちくま新書)
報告文を書く
1) 報告文を書く意義
参加会員は必ず発表内容を報告文として所定の期間内にまとめ、編集委員に提出す
ること。報告文は自己PRであり、研究活動の証明でもある。
2) 報告文の種別
報告文の種別(論文・研究ノート・事例報告など)は会員の自由とする。また、個人研
究発表の報告文は『逐次刊行物研究分科会報告』に掲載する。
2.3.2. 共同研究
問題を設定する
1) 共同研究の意義
共同研究は、内容の深さ、範囲の広さ、個人作業軽減の点で有効な方法である。
2) 研究グループの結成
①会員に共通した問題で、研究希望が多数の場合は、運営委員会の協議を経た上で、
それらの問題に関する共同研究グループの結成を可能とする。
3) 研究グループの要件
① 代表者:グループの代表者1名を選出
② 研究計画:テーマ、年間活動予定、研究方法を明記した計画書
③ 参加人数:共同研究の効果を考えて、規定数7名以上
共同研究を行う
1) 研究の進め方
① 時間:月例会の時間内に行い、時間は各回1時間程度とする
② 参加:会員は共同研究に全員参加する。グループの選択は会員の自由とする
③ 運営:共同研究各グループの運営は、その代表者が責任を持って行う
2) 研究に必要な企画
① 種類:講演、見学、実演(各種デモ)など
② 交渉:企画委員は各種の企画を行い、グループの選択は会員の自由とする
③ 参加:グループ所属に関係なく全員参加とする。ただし、月例会の範囲で設定される
場合(グループのオプション)は、自由参加とする。
cf.マニュアル「研究活動方針」
研究成果を報告する
1) 月例会での報告
グループの代表者は、各回ごとの共同研究内容を月例会(事務連絡)で報告する。
2) 研究成果の報告
共同研究の成果は、その継続期間に関係なく各期毎に報告する。また、研究成果は
『逐次刊行物研究分科会報告』に掲載する。
2.3.3. 資料交換
資料交換の目的
重複等で不要となった各館の逐次刊行物資料を提供し合い、自館の欠号を補充することを目的とする。なお、作業のとりまとめは相互協力委員が中心となって行う。
交換作業要領
1) 交換作業の概要
① 提供リスト」を作成する。
② 4月から12月の例会で「提供リスト」を配布する。
③ 参加館は「提供リスト」をチェックし、希望の資料があれば「希望リスト」を送付する。
④ 受領希望館が複数の場合、提供館が提供先や提供資料を決める。
⑤ 提供館は受領館に資料を送付する。
⑥ 受領館は受領書を送付する。提供館が受領書を必要としない場合は「提供リスト」に
その旨を明記する。
2) 提供リスト
提供館は次の要領で提供リストを作成する。
① 配列:和雑誌、洋雑誌、紀要にわける。
② 項目:資料No.、誌名、巻号、年次、部数、備考の項目を設ける。
③ 誌名:誌名の記述は原則としてCAT記述に従う。紀要は大学等団体名を入れる。
④ 用紙:B5またはB4の二つ折りとする。枚数が2枚以上の場合は左上をホチキスでとめ
る。
3) 希望リスト
書式、送付方法など提供館の指示に従う。
4) 資料の送付
送付方法は郵送、または着払宅急便とする。郵送の場合、受領館は郵送料を同額の
切手で返還する。送付資料が2、3冊の場合は次回月例会に持参してもよい。
交換実績報告
① 相互協力委員は1月の月例会で交換実績表の参加館に配布する。
② 参加館は、結果を交換実績表に記入する。交換実績表に必要な数字(自館の提供、
受領タイトル数、冊数)は各自が控えておく。
③ 参加館は2月末日までにファックスまたは郵便で交換実績表を相互協力委員に提出
する。交換実績がない場合も提出は行う。
④ 相互協力委員は参加館より提出された交換実績表を集計して、結果報告書を作成す
る。交換作業の結果は年度末の月例会で報告する。
提供リストサンプル
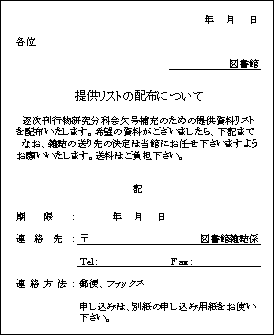
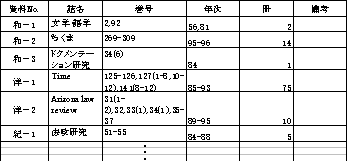

3. 研究活動の資料
3.1. 活動資料
3.1.1. 月例会配布資料
配布資料の種類
月例会で配布する資料は、研究活動に関するものに限定する。したがって、運営委員会が使用する帳票(領収書類)や個別に発行する依頼書は含まない。
1) 研究・調査
① レジュメ、参考資料、参考文献リスト:個人研究発表・共同研究
② アンケート用紙:講習会・合宿、研究テーマ
2) 報告書類
① 逐次刊行物研究分科会報告
② 資料交換実績表
③ 会計報告書(各年度)
3) 連絡・その他
① 逐刊ニュース
② 情報交換:リニューアル・レート、製本価格
③ 見学資料:図書館利用案内、パンフレット、カタログ
配布資料の準備
1) 作業
① レジュメ類:会員は個人研究発表および共同研究に必要な資料(レジュメ類)を準備
し、会員数をコピーして月例会で配布する
② その他:図書館見学などで利用される案内の用意は、会員の自由とする。また、講演
の資料は運営委員が準備する。
2) 負担
原則として、費用は所属大学図書館の負担とする。会員に配布するマニュアル類など
の印刷費用は、分科会の会計負担とする。
3) 形式
レジュメ類のフォーマットは以下のようにする(準拠)。
① 項目:(上から)発表日付(西暦)、テーマ、氏名、所属団体名、内容項目
② サイズ:A4あるいはA3二つ折り数枚程度
③ ナンバー:枚数が多いときは右上端にNo.として数字を入れ、左上端をホチキス止め
cf.マニュアル「個人研究発表」
3.1.2. 逐刊ニュース
発行する目的
通常の月例会活動を円滑に進めるためのNewsletterとして『逐刊ニュース』を発行する。月例会の連絡・報告などは、これに記録として載せる。
逐刊ニュース
1) 編集
① 作業:『逐刊ニュース』の編集作業は、逐刊ニュース編集担当者がする。
② 表示:責任表示は「逐次刊行物研究分科会」(題字欄)
末尾に「発行:~」「代表:~」「編集:~」の表示をする。
③ 内容:原稿(連絡・予定・報告)は会員に依頼する場合がある。
2) 発行
① 標題:『逐刊ニュース』を本題とする。特に他の関連標題は設定しない。
② 発行:「私立大学図書館協会東地区部会研究部逐次刊行物研究分科会」発行
巻次は通号表示とし、「No.-」の形式を採用する。
③ 形態:大きさは、B4版1枚二つ折り程度。刊行頻度は月刊(年に10回発行)
④ 用紙などの費用は分科会の会計負担とする。
3) 配布
① 場所:月例会の会場、出席会員に配布
② 発送:休会者には月例会会場校会員から発送
内容とその構成
1) 予定
月例会における研究活動の具体的な項目
① 月例会当日の具体的な進行予定
② 次回月例会の開催予定:会場(連絡先)、日時、内容
③ 共同研究などの連絡事項
2) 報告
前回の月例会の概要、合同会議(私大図協)の内容、講演の要点など
3) 記事
逐次刊行物・大学図書館関係のもの、その他実務に役立つもの
3.1.3. 事務文書
文書作成の前提
1) 作業-文書の類別
① 類別:企画作業、連絡作業、会計作業
② 要件:文書は「誰が(発信者)、誰に(受信者)、何を(内容)何時(日付)」が重要
2) 不要文書を作成しない
必要最小限の文書だけを作成し、不要な文書は作成しない。電話で代替可能な内容
はなるべく文書化しない。また、ファックスや電子メールで済む内容は郵送にしない。
3) 書式の統一化(フォーマットづくり)
① 受信者:書式の統一は文書の受取る側(読み手)の時間短縮につながる
② 発信者:書式を統一しておけば、様々な場合に対応して文書の作成が容易
事務文書一覧
| 作業 |
文書名 |
受信者 |
サイズ |
| 企画 |
共同研究テーマ(方法)提案書 |
会員 |
A4 |
| 企画 |
夏期研究合宿企画書(要領) |
会員 |
A4 |
| 企画 |
会場校・個人研究合宿企画書 |
会員 |
A4 |
| 連絡 |
ファックス送信用紙 |
会員 |
A4 |
| 連絡 |
研究分科会開催通知 |
私大図協 |
A4 |
| 連絡 |
研究分科会開催予定(2ヶ月予定) |
図書館長 |
A4 |
| 連絡 |
『分科会報告』送付書 |
送付先 |
A4 |
| 連絡 |
研究分科会会員募集要領 |
図書館長 |
A4 |
| 連絡 |
月例会資料送付書 |
月例会欠席会員 |
A5 |
| 依頼 |
夏期研究合宿依頼書(分科会) |
図書館長 |
A4 |
| 依頼 |
夏期研究合宿依頼書(私大図協) |
図書館長 |
A4 |
| 依頼 |
講師依頼書 |
講師 |
A4 |
| 依頼 |
『分科会報告』広告掲載依頼書(要領) |
広告依頼者 |
A4 |
| 依頼 |
『分科会報告』広告料納入願い |
広告主 |
A4 |
| 報告 |
研究分科会活動計画 |
私大図協 |
A4 |
| 報告 |
研究分科会活動報告 |
私大図協 |
A4 |
| 報告 |
夏期研究合宿実施計画 |
私大図協 |
A4 |
| 報告 |
資料交換実績表 |
会員 |
A4 |
| 会計 |
会計決算報告(一般) |
私大図協 |
A4 |
| 会計 |
会計決算報告(報告書) |
私大図協 |
A4 |
3.2. 研究報告
3.2.1. 報告書
報告書の作成
1) 研究成果の公表
研究成果は主に『逐次刊行物研究分科会報告』として発表する。
2) 報告書の構成
報告書の発行に関しては『学術雑誌の構成とその要素』(SIST-07)に準拠する。
① 構成:表紙(背、裏を含む)、標題紙、目次、本文、奥付は必須
② 編集:編集者名『逐次刊行物研究分科会報告』編集委員会
③ 発行:発行者名「私立大学図書館協会東地区部会研究部逐次刊行物研究分科会」
発行年は西暦の年月日を使用する
④ 誌名:本標題「逐次刊行物研究分科会報告」
英語標題は、表紙、英語目次、奥付などに記載する
⑤ 巻号:号数は通号で表示、形式は「第一号」とする。年次は西暦を使用
⑥ 頻度:年刊を原則とする
⑦ 識別:識別記号ISSN “0388-1083”
3) 発行
① 部数:約400部(頒布270、寄贈20、会員30-40、在庫70)
② 価格:ページ数・頒布数を考慮して編集委員会で決定。発行費用と回収予想金額とを
比較して赤字にならないよう調整
編集作業
1) 内容
各期の研究活動を中心とし、活動・会計報告、講演録も含む。
① 個人研究・共同研究の論文、研究ノート、事例報告
② 講演者の寄稿または講演録
③ 活動・会計報告、アンケート集計結果、会員名簿など
2) 編集
編集委員は編集の中心となり、運営委員は編集委員を補助する。
① 会員・講師への原稿依頼、執筆要領、投稿規定の説明
② 校正・内容校正・レイアウト
③ 業者との交渉(見積・発注・検収)、広告の依頼
* 関連項目:マニュアル「原稿募集要項」、「報告書発送作業」も見よ
3.2.2. 原稿募集要領
募集原則
1) 資格
『逐次刊行物研究分科会報告』の応募資格は次のとおり。投稿先は各期における編
集委員会宛とする。
① 逐次刊行物研究分科会の現会員および元会員
② 大学図書館の職員で逐次刊行物業務に関係する者
③ 月例会の講演者、編集委員会からの執筆依頼者
2) 内容
次のいずれかで執筆者自身の未発表原稿に限る。また、原稿は原則として返却しない。
① 逐次刊行物に関係する論文、研究ノート
② 逐次刊行物業務に関する事例および調査報告
③ 月例会などの見学に関する感想・意見
3) 別刷
論文、マニュアルなどは必要に応じて別刷を作成する。また、謝礼として一論文につ
き本誌1部と別刷を20部、著者に贈呈する。
執筆要領
1) 書式
① 字数:論文・報告は、原則として、10,000字以上12,000字以内
② 原稿:原則としてワープロ原稿(横書)とする。A4・22字×40行
③ 記載:原稿は原則として次の順で執筆
標題、英語標題、執筆者名(付:ひらがな読み)、所属、本文、註、引用
(参考)文献
2) 表記
表記は特別な理由がない限り、常用漢字・現代かなづかい・算用数字を用いる。
3) 引用
引用・参考文献の書き方は、次の基準に準拠する。
科学技術情報流通基準SIST-02 (1984) 「参照文献の書き方」
それ以外の方法で書く場合は、形式を統一し出典を明示する。
3.2.3. 報告書発送作業
配布先の種別
1) 配布(無料)
会費を納入して登録されている現会員には無料配布
2) 寄贈(限定)
① 上部団体、運営委員会で寄贈を決定した団体
上部:私立大学図書館協会東地区部会研究部(担当理事校代表者宛)
納本:国立国会図書館収書部国内資料課
協会:日本図書館協会など
② 逐次刊行物研究分科会活動の関係者
前期の代表、講演者、講師(予定者を含む)、会場提供者(見学先など)
③ 報告書の作成に関係する者
寄稿者、資料提供者、広告主
3) 頒布
頒布先リストに登録されている継続購読の団体・個人。
発送ファイルの管理
① ファイル:発送先をパソコンで管理し、発送時にリストを出力する
② 項目:発送先、発送先ヨミ、郵便番号、所在地、配布種別(寄贈・頒布)、発送種
別(継続・非継続)、注記
発送手順
1) 予備作業
① 発送先リスト(チェック用)、アドレスシール(タック・フォーム)、封筒を用意
② 必要書類(見積・納品・請求)、送り状(寄贈・頒布の2種類)を作成
③ 寄贈(報告書、送り状)と頒布(報告書、送り状、書類)の区別
2) 発送手順(物・人・場所)
① 日時(発行後なるべく早め)、作業場所(集合しやすい会員校)の決定
② 発送は原則として編集委員が作業する
③ 報告書、封筒+アドレス・シール、必要書類、振込用紙、送り状をセット(寄贈・頒布)
*宣伝(ダイレクトメール):非継続購読者には目次のコピーを送り、購入依頼をする。
3.3. 引継資料
引継資料の内容
1) 引継資料の担当
運営委員は、研究会の運営維持のために引継資料の保管を分担して行う。引継担当
の委員が決定していない場合は、原則として代表が代行する。
2) 引継資料の範囲
研究会でいう引継資料とは、研究会の運営維持に必要な共有資料のすべてであり、
事務文書の他、領収書、通帳、会印などの物品を含む。
3) 引継、文書の種別
① 文書:事務文書フォーマット・サンプル・マニュアル類、報告書発送先リスト(フロッ
ピー)
② 会計:会計報告書(年度別)、領収書、通帳
③ 物品:会印、封筒、葉書、報告書バックナンバー
引継資料の保管
1) 保管の原則
運営委員が個人的に保管可能な量は限界がある。必要なもの以外は廃棄すること。
不要な文書を作成しないのと同様、不要な資料は所蔵しない。
① 場所:ひとつの担当に関する資料は一人で1ヶ所に保管する。
② 原紙:オリジナルだけ保管する。不要なコピーは作らない。
③ サイズ:文書のサイズを統一する。
2) 廃棄基準
用済み、重複、通知、回答
① 用済みの案内状、期間経過などを基準にする
② 用済みのコピー文書(オリジナルの所在が明らかなもの)
③ 用済みの依頼書、企画書
④ 重複して保管している文書
⑤ 再生が容易な文書
⑥ 礼状、受領書
⑦ 保管期間が過ぎた文書
⑧ 保存期間が過ぎた領収書
⑨ 報告書の原稿(報告書発行後)
⑩ 前年度の会員申込書、レポート
参考文献リスト 1997
* タイトルをより多く収録するために、書誌データは識別可能なレベルにした。
[逐次刊行物全般]
□学術雑誌.JLA 1976
□逐次刊行物.JLA (図書館の仕事17) 1986
□逐次刊行物.JLA (図書館員選書5) 1986
□大学図書館の管理と運営.JLA 1992
□大学図書館の理論と実践.日本私立大学協会 1990
□情報管理.東京書籍 (現代図書館学講座9) 1984
□資料整理法特論.東京書籍 (現代図書館学講座8) 1984
□書誌と索引.堀込静香.補訂版 JLA (図書館員選書19) 1996
□図書館・情報学のための調査研究法.津田良成.勁草書房 1986
□図書館資料の受入.S. フォード.勁草書房 1984
□Serials accessioning manual. LC
□Serial publications. A. D. Osborn. 3rd ed. 1980
[雑誌]
□逐次刊行物研究分科会報告
□図書館雑誌
□大学図書館研究
□現代の図書館
□専門図書館
□医学図書館
□薬学図書館
□情報管理
□情報の科学と技術
□整理技術研究
□Library Journal
□Library and Information Science
□Library Trends
□Library Resources and Technical Services
□Serials Librarian
□Serials Review
[目録規則、基準類]
□日本目録規則1987年版=NCR87
□英米目録規則第2版=AACR2
□コンサイスAACR2
□国立国会図書館逐次刊行物目録規則1982=NCLCRs(赤本)
□国際基準書誌記述(逐次刊行物用)=ISBD(s)
□Anglo-American cataloguing rules. 2nd ed. 1988 rev. =AACR2R
□LC ARULE Interpretations of bulletin. LC=CSB
□Guidelines for the Application of the ISBDs to the description of component
parts.
IFLA UBCIM=ISBD(cp)
□International guidelines for the cataloging of newsoaoers. IFLA UBCIM.
[MARC]
□マークをうまく使うには、黒沢正彦、西村徹編
□典拠ユニバーサルフォーマット
□JAPAN/MARCマニュアル.逐次刊行物編
□USMARC bibliographic format (with code lists)
□USMARC authority format
□Reference manual for machine-readable bibliographic description. 2nd
rev. ed.
=UNISIST RM2
[学総目]
□学術雑誌総合目録和文編全国調査データ記入要項1995
□学術雑誌総合目録欧文編全国調査データ記入要項1992
□目録システム利用マニュアル.データベース編=目録情報の基準.第2版 1990
□目録システム利用マニュアル.検索編.第3版 1992
□目録システム利用マニュアル. 登録編.第3版 1993
□オンライン・システムニュースレター
□目録システムコーディング・マニュアル
[書誌記述、配列]
□新目録と書誌情報.丸山昭二郎
□洋書目録入門.マニュアル編
□洋書目録入門.つくり方編
□SISTハンドブック.JICST
□ISDS manual
□Handbook for AACR 2 1988 revision. ALA 「Serials」 p.219-240
□Serials cataloging handbook. ALA
□A Practical approach to serial cataloging
□Newspaper cataloging manual
□A Manual of style for authors, editors and copywriters 1969
□目録編成規則.日図研
□議会図書館配列規則
□LC romanization table (CSB所収)
□Notes for serials cataloging
□Notes for catalogers: a sourcebook for use with AACR2
□Notes in the catalog record on AACR2 and LC rule interpretations
□Lists of generic terms in languages used in ISDS-SEA member countries
[専門辞典類]
□図書館情報学ハンドブック
□図書館ハンドブック
□ALA図書館情報学辞典
□The ALA glossary of library and information sciences
□日本書誌学用語辞典
□図書館学辞典
□洋書辞典
□図書館用語集.改訂版
[ニューメディア関連]
□世界CD-ROM総覧
□オンラインデータベースディレクトリー.週刊東洋経済臨時増刊
□オンラインデータベース活用事典
[目録、便覧、年鑑]
□国立国会図書館所蔵国内逐次刊行物目録
□国立国会図書館所蔵外国逐次刊行物目録
□学術雑誌総合目録.和文編
□学術雑誌総合目録.欧文編
□日本科学技術関連逐次刊行物総覧
□雑誌新聞総かたろぐ
□日本雑誌総覧
□日本年鑑総覧
□出版年鑑
□日本新聞雑誌便覧
□日本各種団体名鑑
□全国学術研究団体総覧
□全国大学職員録
□大学研究所要覧
□ 日本の図書館
□ 図書館年鑑
□ライブラリーデータ
□Ulrich's
□The Serials Directory
□The Standard Periodical Directory
□The World of Learning
□World Guide to Libraries
[主題付与、検索]
□日本十進分類法=NDC
□国立国会図書館分類表=NDLC
□国際十進分類法=UDC
□Dewey Decimal Classification
□米国議会図書館分類表=LCC
□基本件名標目標=BSH
□国立国会図書館件名標目表=NDLSH
□英国図書館作成件名標目(固有名件名)=BLSH
□米国議会図書館件名標目表=LCSH
私立大学図書館協会東地区部会研究部分科会申し合わせ
昭和48年4月1日制定
昭和55年6月18日改訂
平成7年9月25日改訂
第1条 この申し合わせは、私立大学図書館協会東地区部会研究部に研究分科会を置く事を
定める。
第2条 本研究分科会は、私立大学図書館協会東地区部会研究部細則の当該条項に則っ
て活動するものとする。
第3条 各研究分科会は、以下の要件を備え、かつ、それぞれ異なった大学に属する者5名
以上をもって構成されるものとし、研究部運営委員会の議を経て研究部理事の承認
を得なければならない。
① 当該年度の研究テーマ
② 当該年度の研究回数
③ 当該テーマの研究に必要とされる条件
④ 会費徴収額
第4条 各研究分科会は、会の代表者として、1名以上の研究分科会代表者を置かなければ
ならない。
第5条 各研究分科会の活動期間は2年とし、更新することができる。更新にあたっては、研
究部運営委員会の議を経て研究部理事の承認を得なければならない。
第6条 新規に研究分科会を発足するにあたっては、研究部理事に対し、第3条の要件を前
年度12月末までに示さなければならない。
第7条 研究部理事は、研究分科会の更新年度初頭、加盟館代表者に、第3条各号の事項
を通知し、加盟館における参加者選定の基準を示さなければならない。
第8条 加盟館代表者は、更新年度初頭に、各研究分科会の参加者を決定し、研究部理事
に通知するものとする。
2 研究部理事は、この通知に基づき、当該研究分科会代表者に諮ったうえ、各研究分
科会の会員として登録する。
第9条 各研究分科会の活動期間中に、途中入退会者があった場合、研究分科会代表者は
書面をもって、研究部理事に通知するものとする。
第10条 各研究分科会は、研究部より助成金を受けることができる。
第11条 研究分科会代表者は、当該研究分科会を主宰するとともに、毎月末までに、翌月
の開催計画を、研究部理事に連絡するものとする。
第12条 研究分科会代表者は、毎年1会研究部理事に、研究分科会の活動状況および会計
報告をしなければならない。
第13条 研究分科会代表者は、研究部理事の求めに応じて、運営委員会に出席することが
できる。ただし、議決権をもつことができない。
第14条 各研究分科会は、その研究の成果を研究部の開催する研究会において発表しなけ
ればならない。
第15条 本申し合わせの改廃は、研究部運営委員会の議を経て研究部理事の承認を得て行
うものとする。
附 則
1 研究分科会の発足および更新にあたって第3条を満たしていない場合でも、研究部
理事の承認を得た場合には、準研究分科会として活動することができる。
2 準研究分科会として承認された場合には,第10条を除き、研究部より可及的な援助
を受けることができる。
3 本改訂は、平成7年11月13日より実施する。
私立大学図書館協会東地区部会研究部細則
昭和29年4月1日 制定
昭和34年5月8日 改訂
昭和35年10月14日 改訂
昭和44年2月18日 改訂
昭和63年6月28日 改訂
第1条 本研究部は、私立大学図書館協会会則第35条第2項、第39および第40条に基づい
て定められたもので、私立大学図書館協会東地区部会研究部(以下研究部と称す
る)と称し、事務所を私立大学図書館協会(以下本協会と称する)東地区部会研究部
担当理事校におく。
第2条 本研究部は、本協会東地区部会に所属する図書館の館員で構成する。
第3条 本研究部は、館員の自由な専門的調査、研究を助長し、その成果を改善、向上させ
ることを目的とする。
第4条 本研究部は、前条の目的達成のために次の事業を行なう。
1. 研究部会の開催
2. 研究分科会の育成
3. 研究集会の促進
4 . 機関誌の発行
5. 他地区部会研究会との連絡、インフォメーションの交換
6. その他研究部の目的達成に必要な事項
第5条 研究部会は少なくとも年2回開き、研究発表および研究部の事業についての報告そ
の他を行う。会場は加盟校が輪番で担当する。
第6条 研究分科会は各グループごとに適宜開催し、その研究の進行状況、成果その他を研
究部理事および研究部会に報告するものとする。各分科会は本研究部より助成金を
受けることができる。
第7条 研究集会は、加盟校各館において適宜開催し、研究部理事に報告するものとする。
第8条 機関誌は第4条の各事業の状況および研究成果を発表するもので、研究部理事が
編集の責任にあたる。ただし、当分の間本協会会報をこれにあてる。
第9条 本研究部には、次の役員をおく。
1. 研究部理事 1名
2. 常任幹事 8名(理事校3名その他5名)
3. 幹事 加盟校各館1名
第10条 研究部理事には、本研究部担当理事校代表者があたり、本研究部を代表し、かつこ
れを統轄する。
第11条 常任理事は、隔年4月幹事のうちから幹事会がこれを選出し、本協会東地区部会の
役員会の承認を得た上、研究部理事をたすけて本研究部の運営にあたる。
第12条 幹事は、加盟校各館より隔年4月1名を選出し、本研究部の運営について協議する。
第13条 本研究部には、部の運営を円滑ならしめるため、次の機関をおく。
1. 常任理事会
2. 幹事会
第14条 常任理事会は、研究部理事が少なくとも年3回招集し、次の事項を行う。ただし必要
に応じて各研究分科会世話人あるいは当該研究部会会場校代表の出席を求めるこ
とができる。
1. 研究部の事業計画
2. 研究部会の運営に関する事項
3. 研究分科会間の連絡、インフォメーションの交換
4. 研究部機関誌の編集、発行
5. その他本研究部の運営に関する事項
第15条 幹事会は、研究部理事が隔年1回以上招集し、次の事項を審議する。
1. 常任幹事の選出
2. 本研究部の目的達成に必要な事項
第16条 本研究部の経費は、本協会東地区部会の助成金およびその他をあてる。ただし、必
要に応じて実費を徴収することができる。
第17条 本細則の改廃は、本協会東地区部会の承認を要する。
附 則
1. 本細則は昭和29年4月1日よりこれを実施する。
2. 本改訂細則は昭和34年5月8日よりこれを実施する。
3. 本改訂細則は昭和35年10月14日よりこれを実施する。
4. 本改訂細則は昭和44年2月18日よりこれを実施する。
5. 本改訂細則は昭和63年6月28日よりこれを実施する。